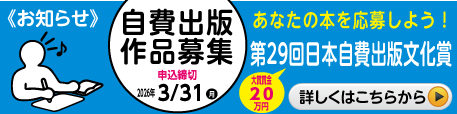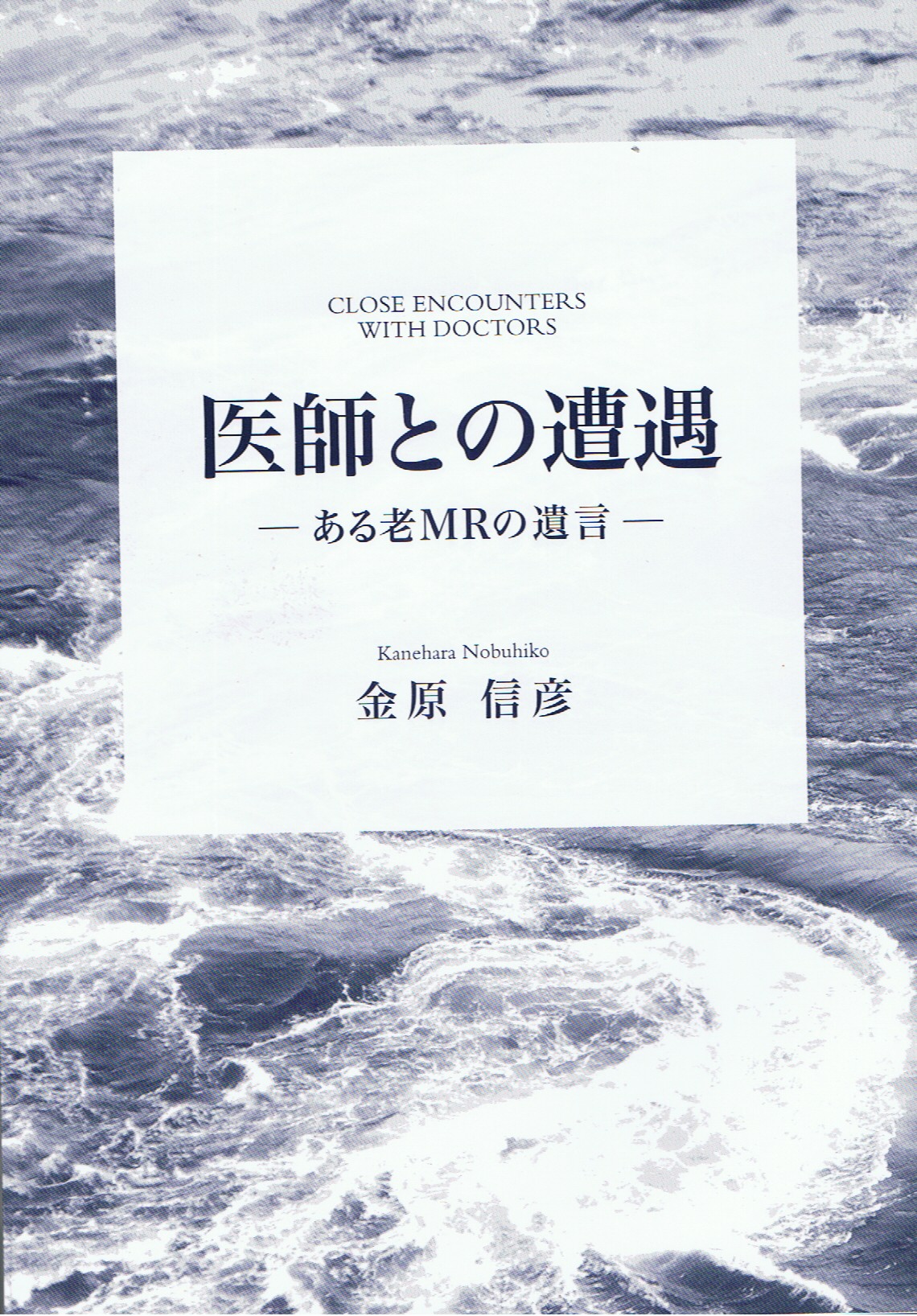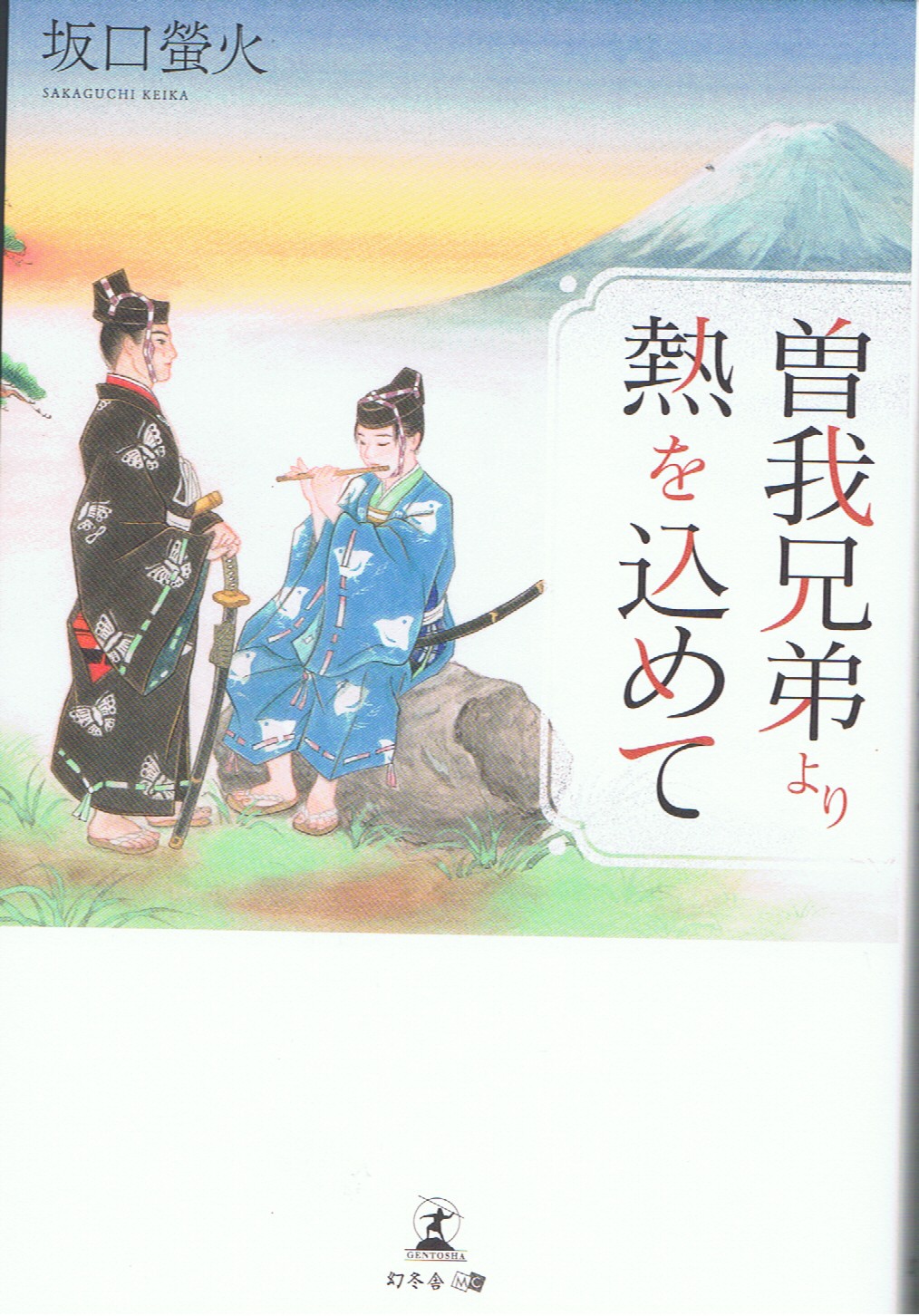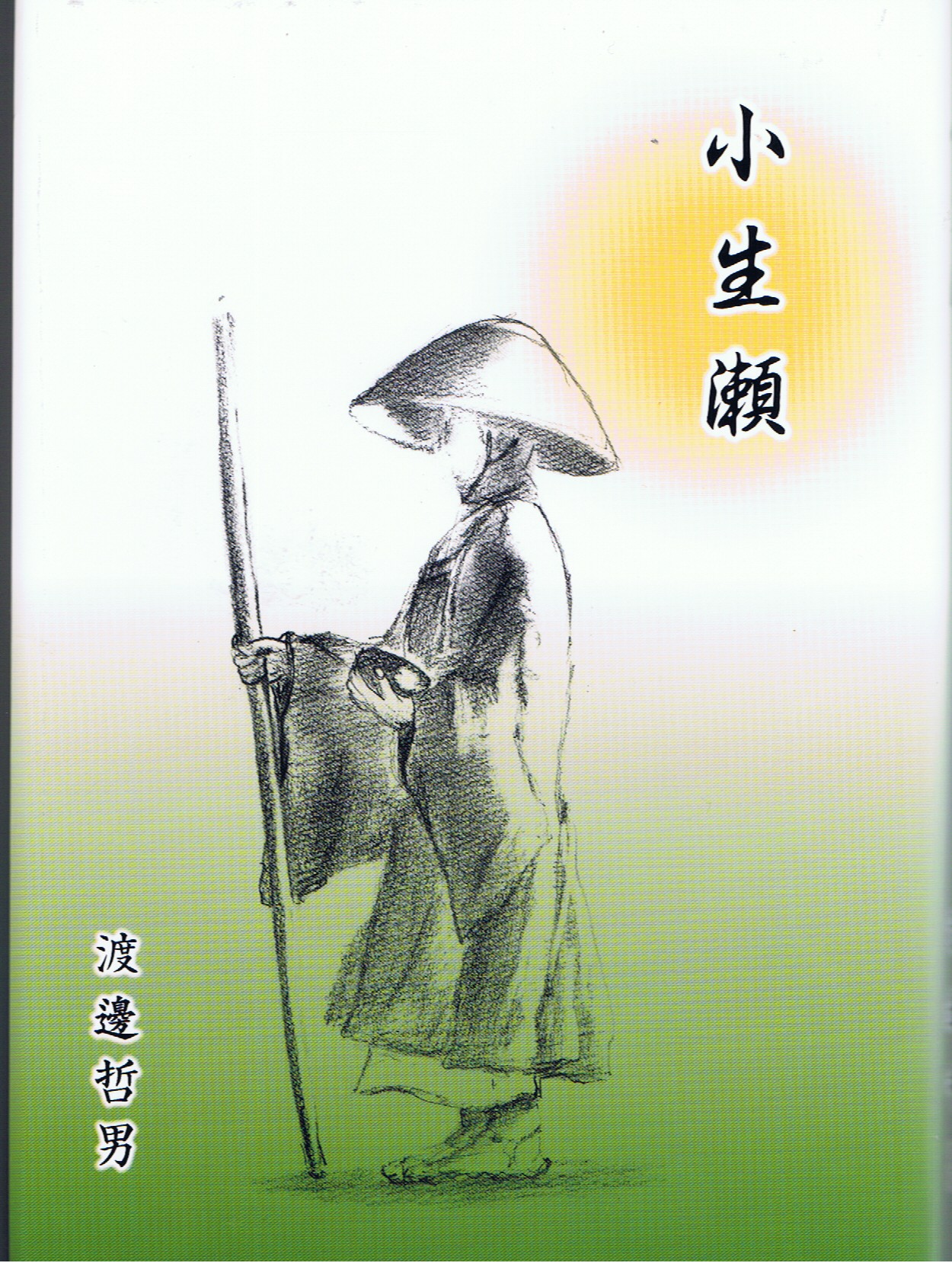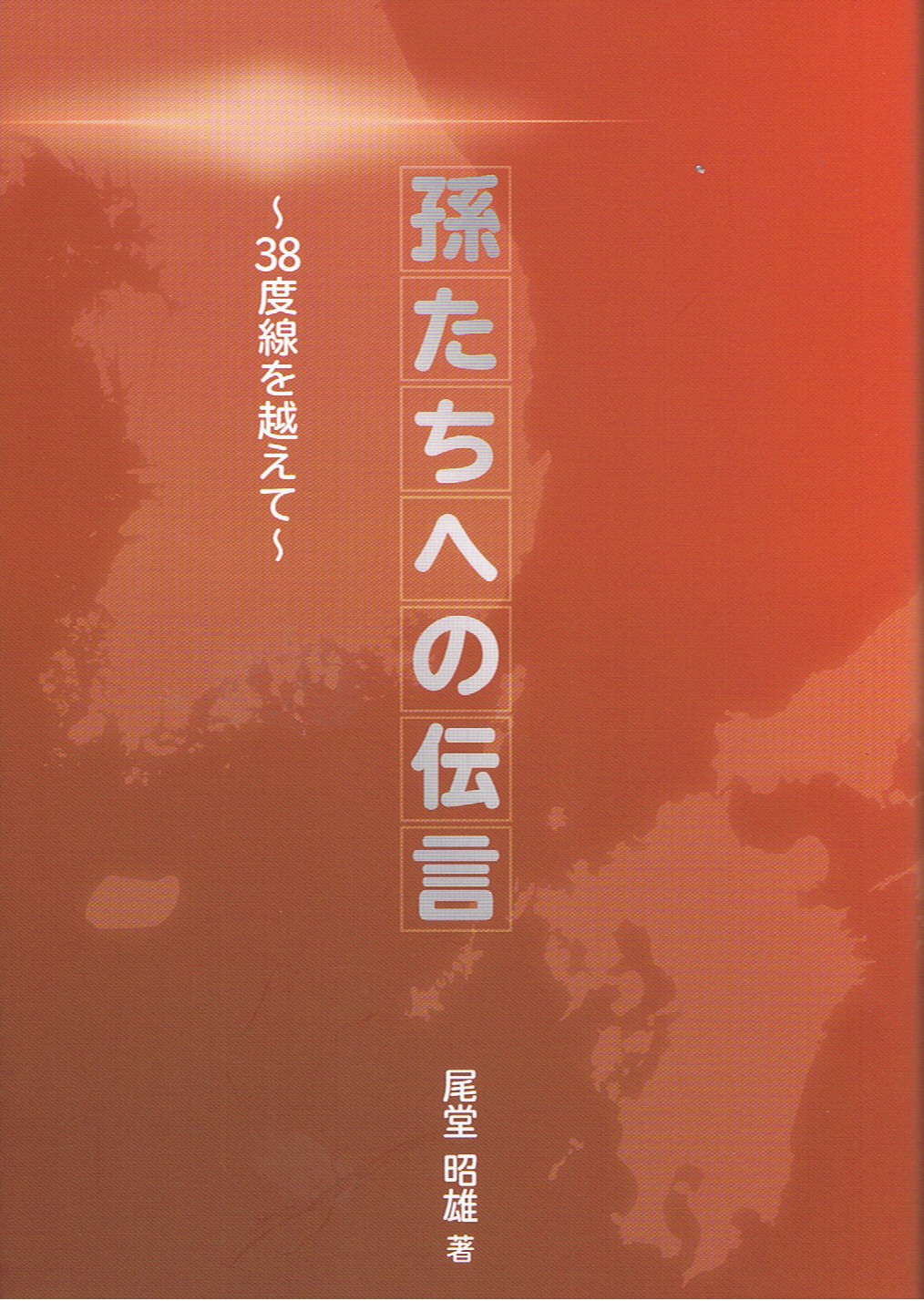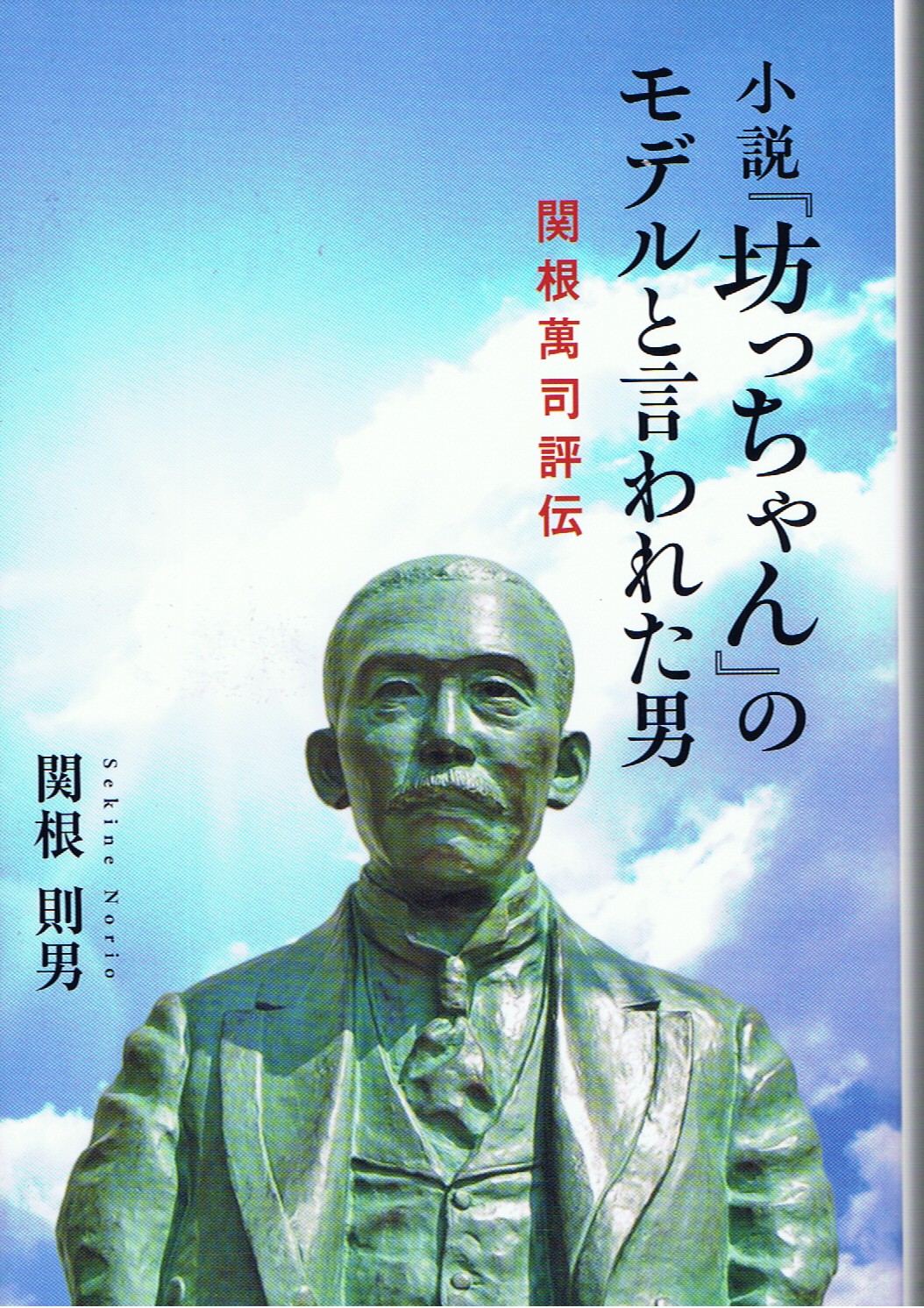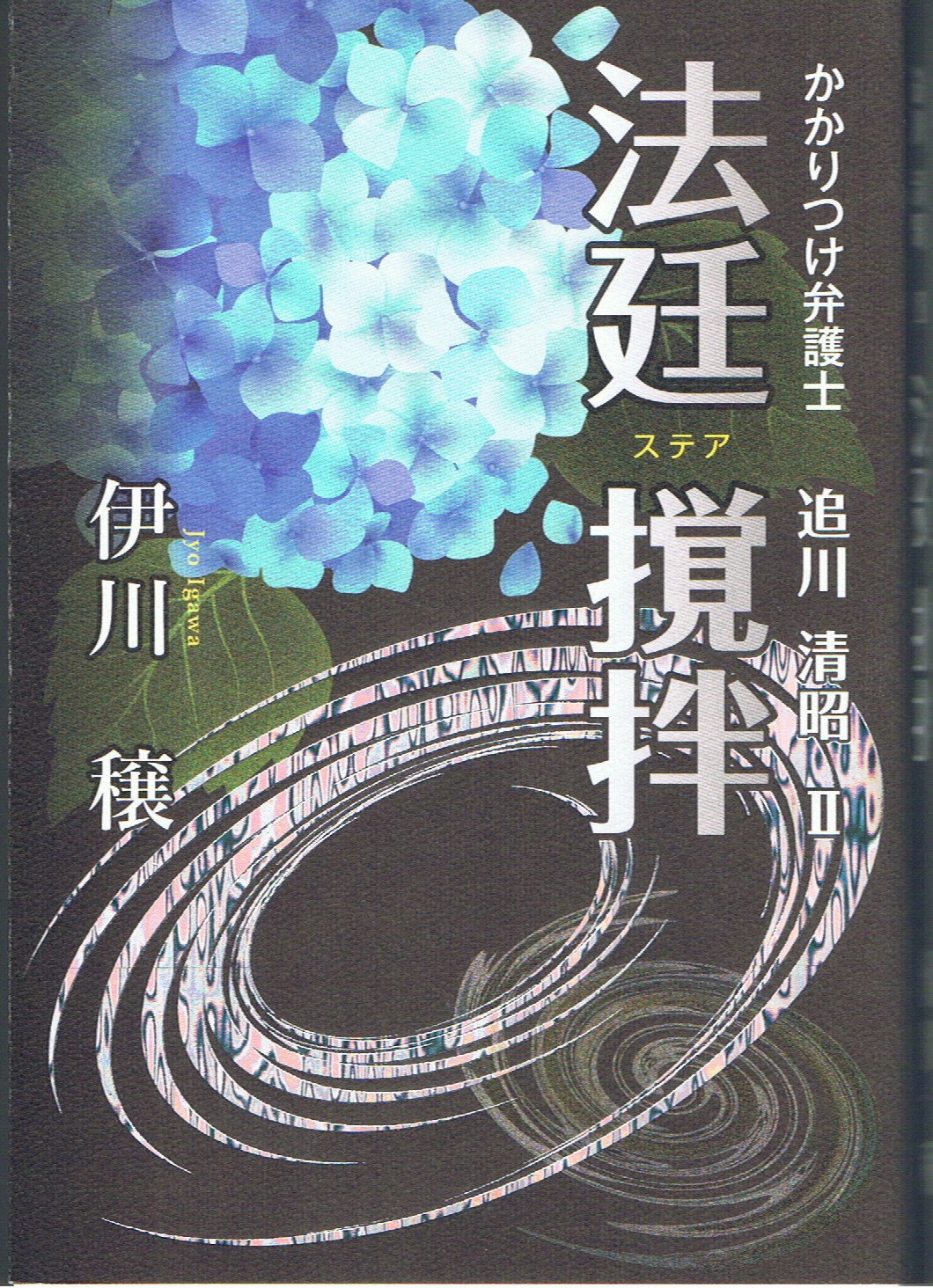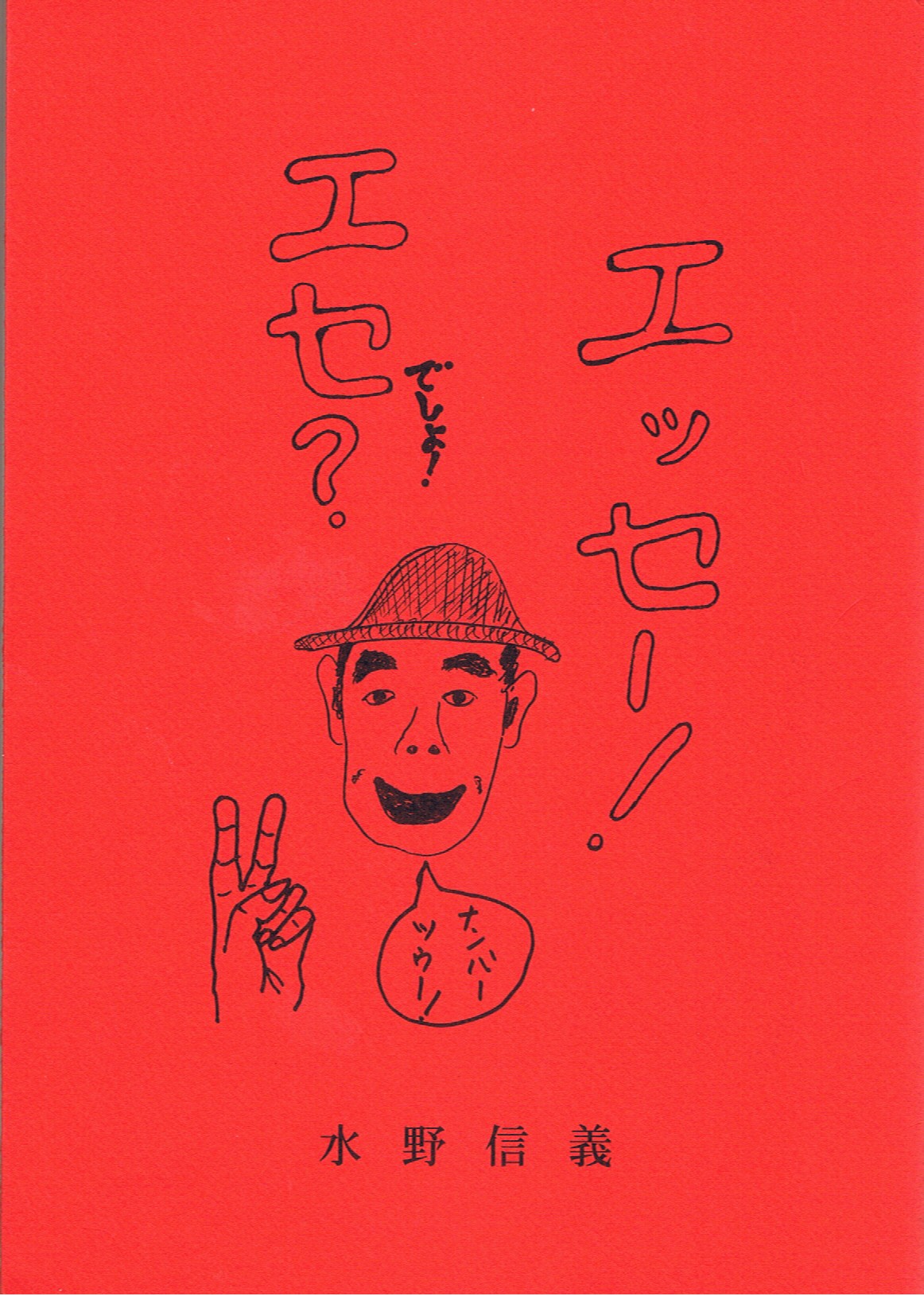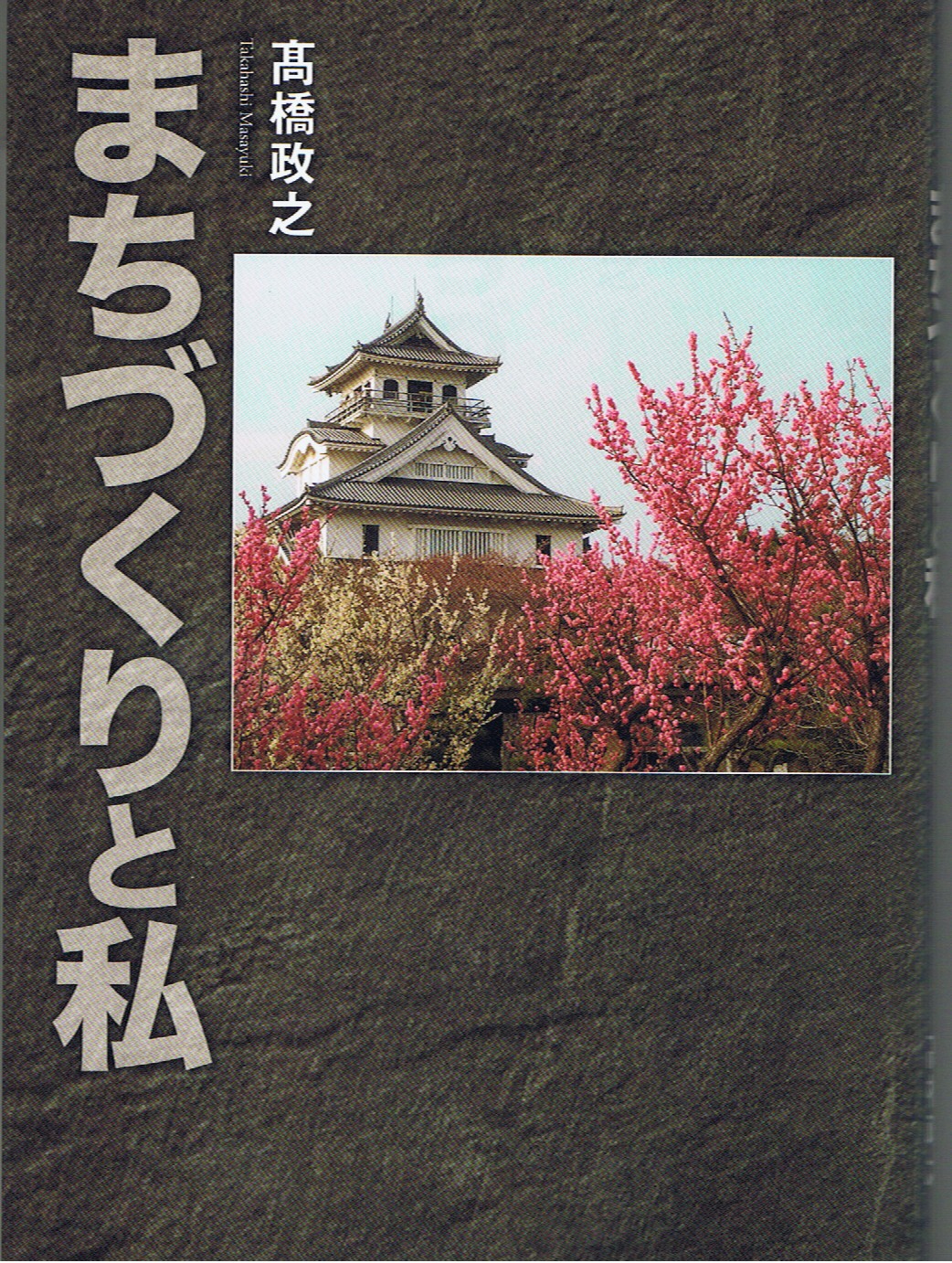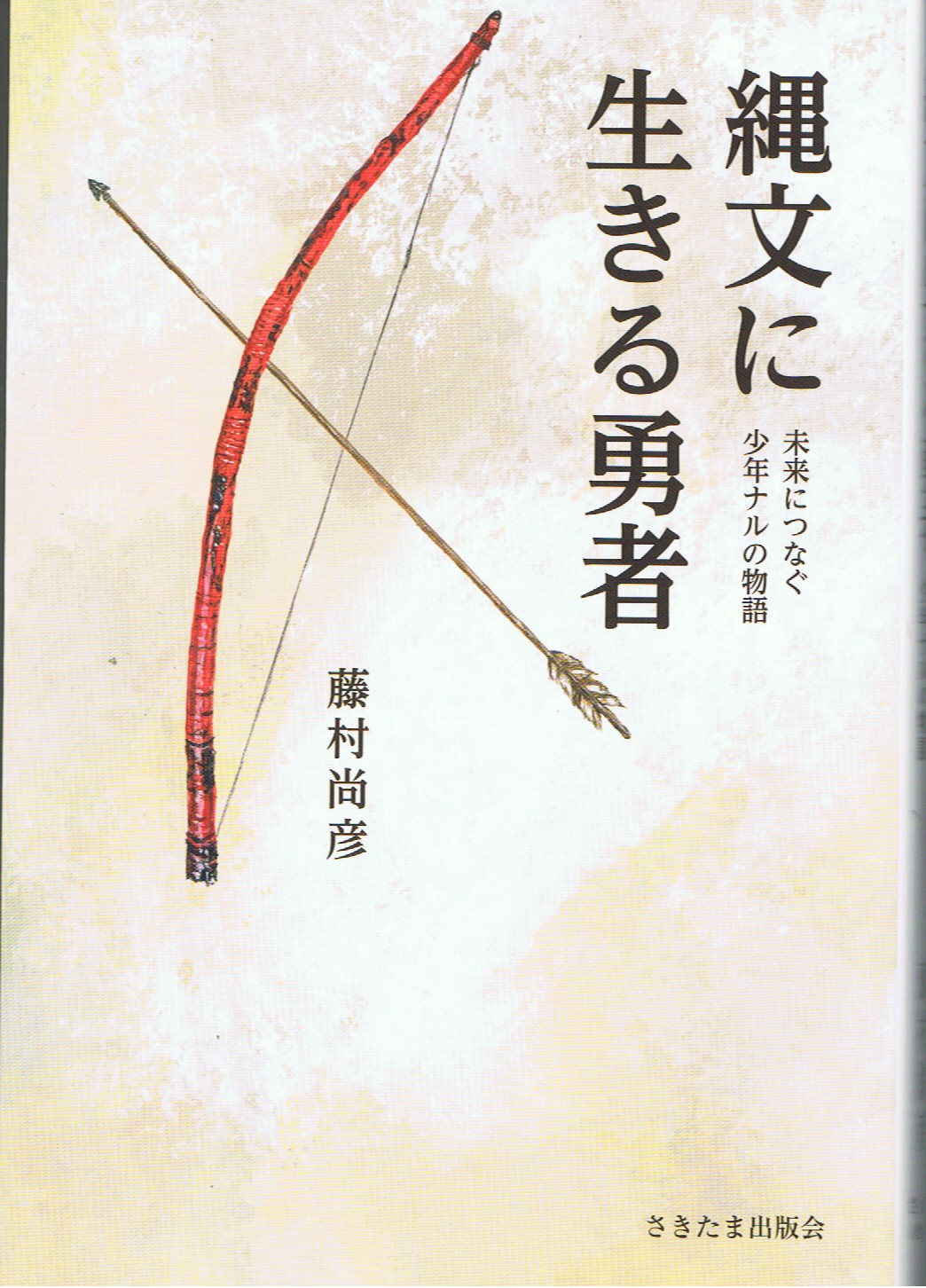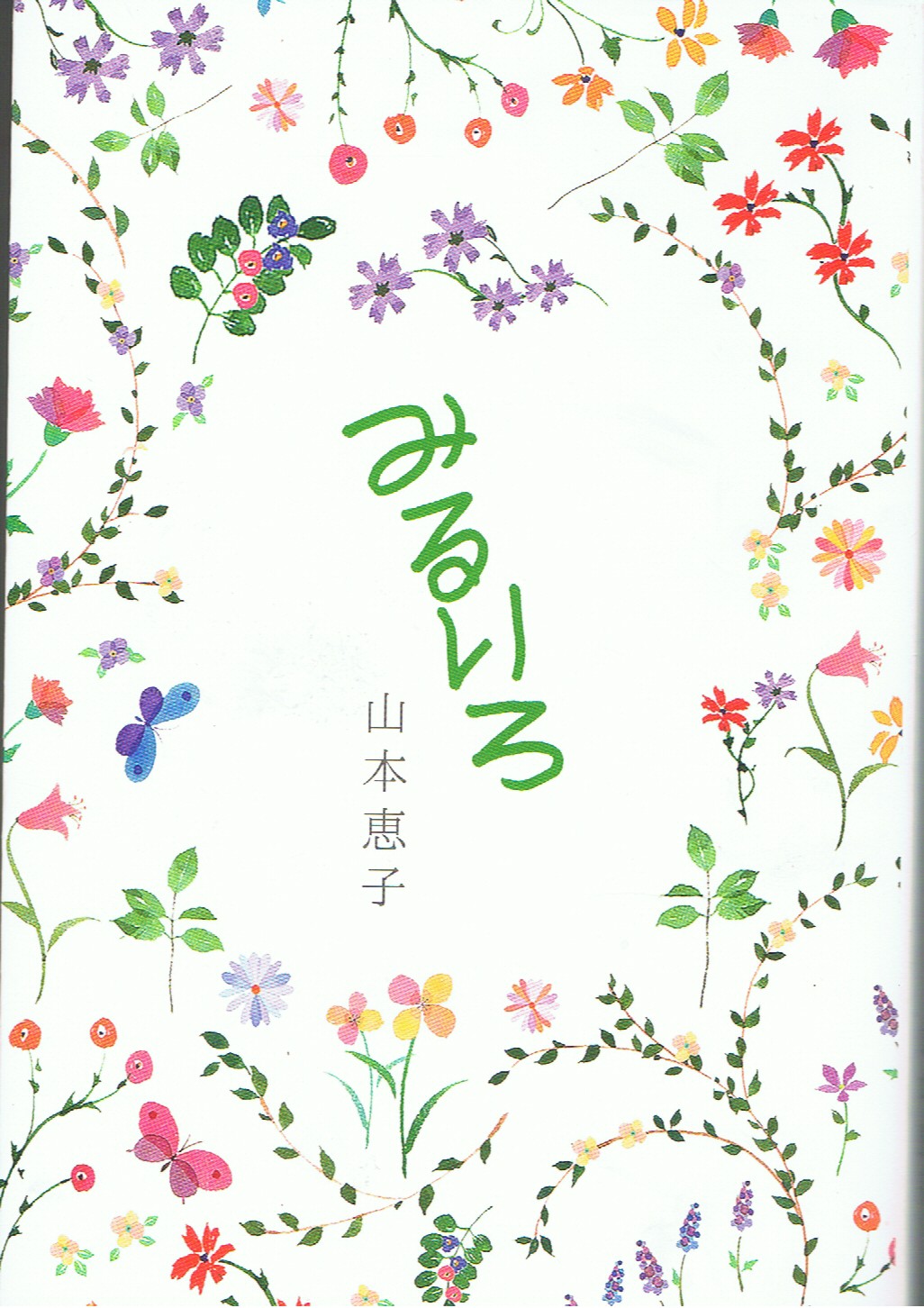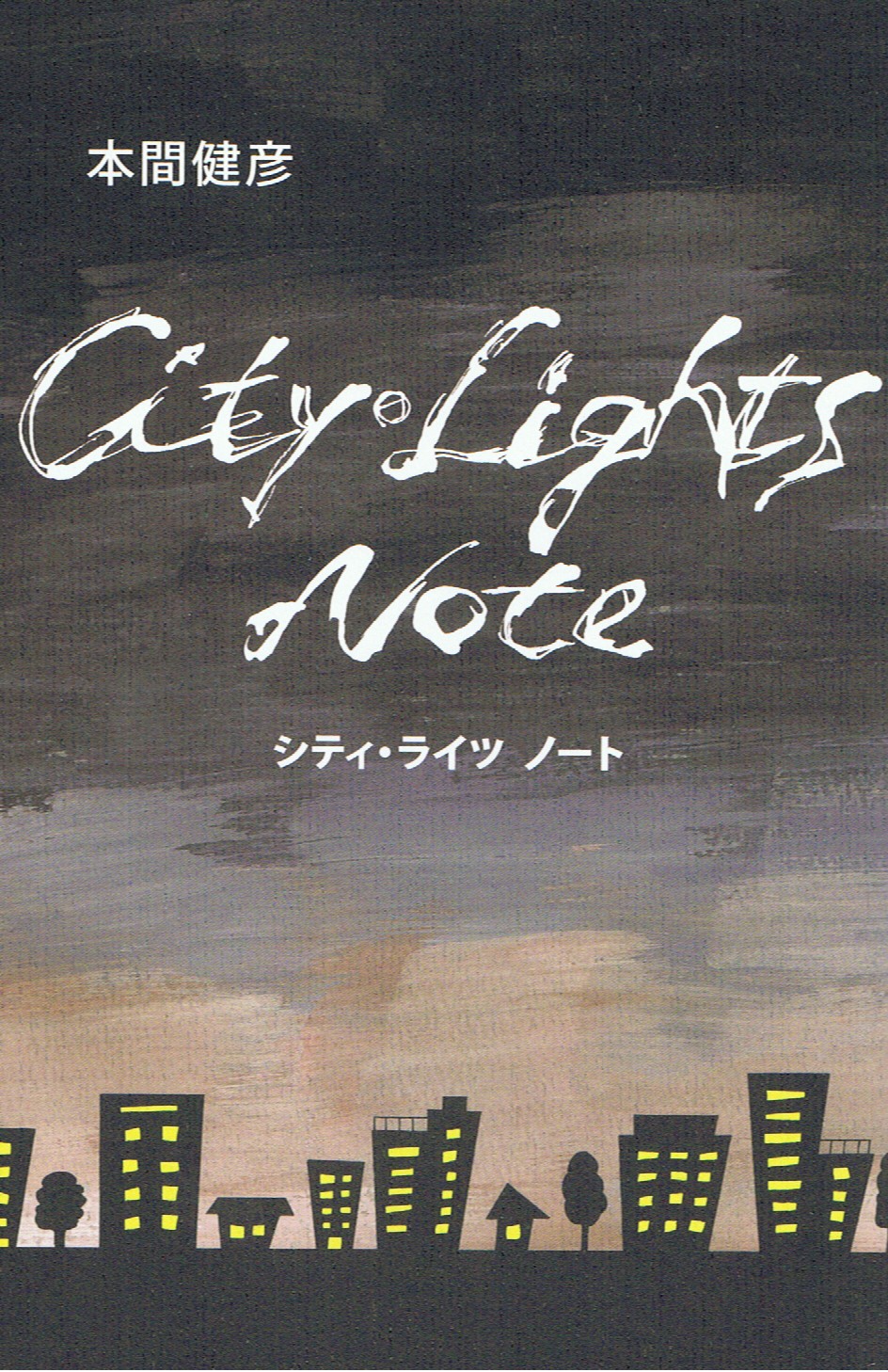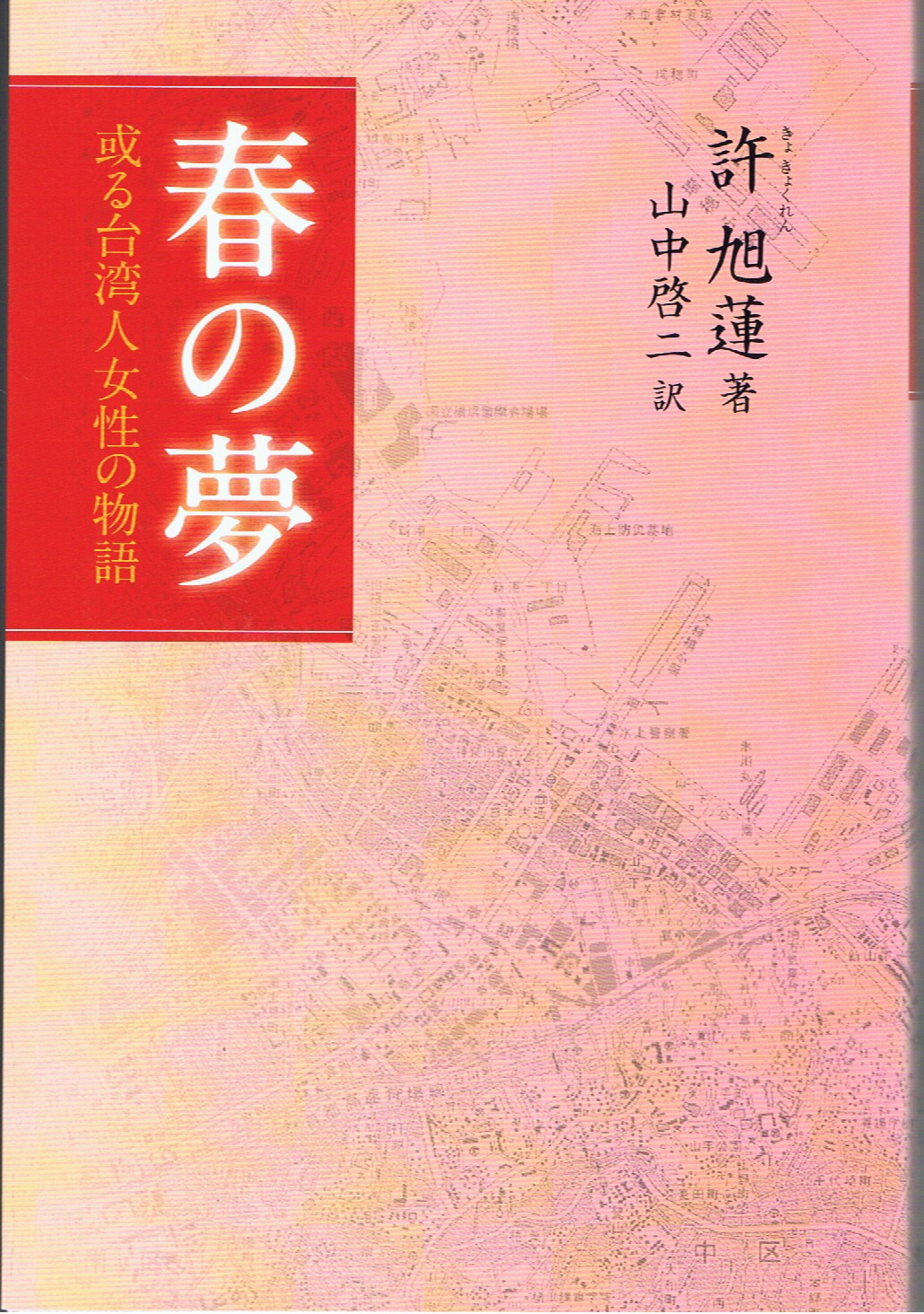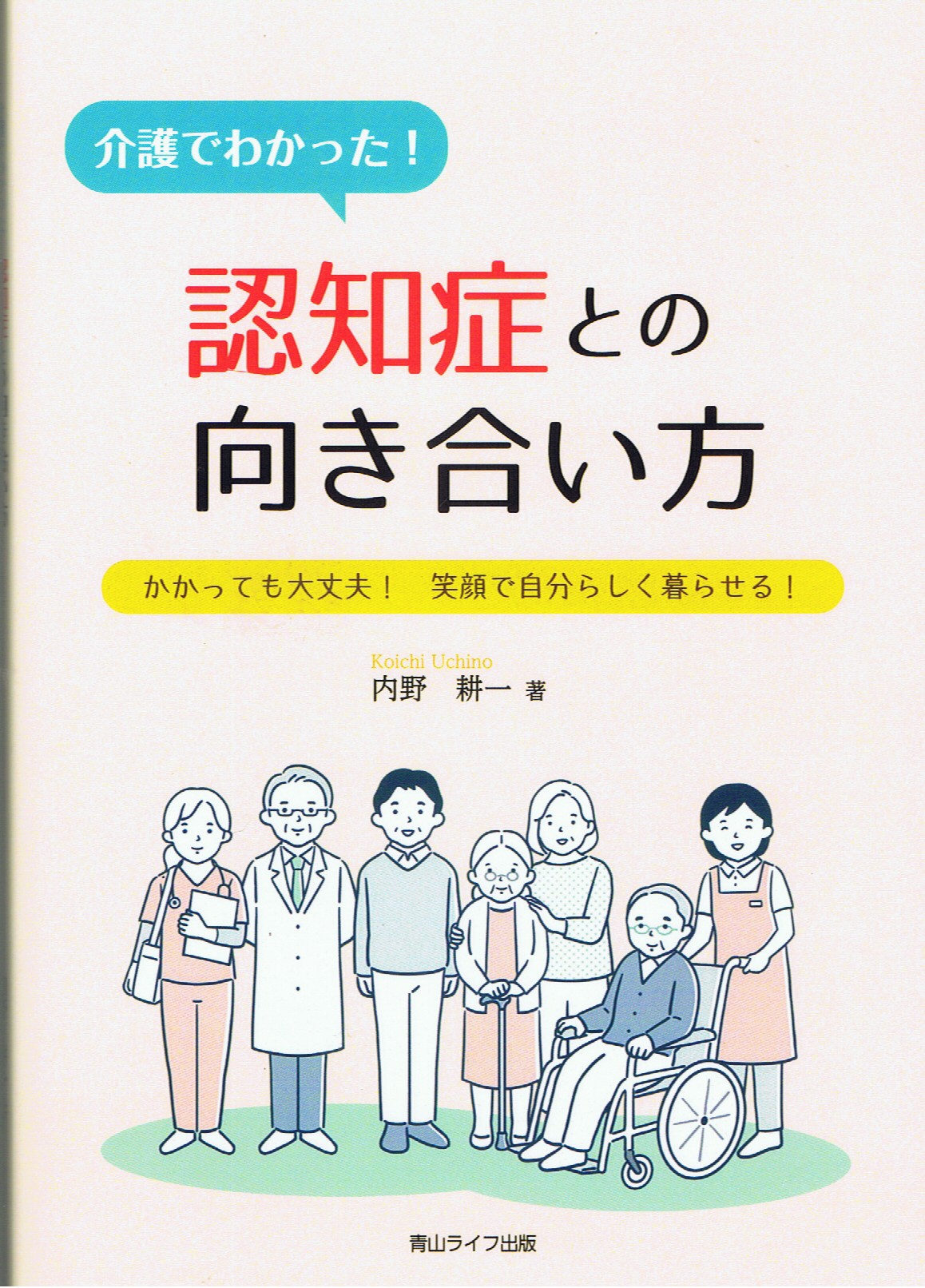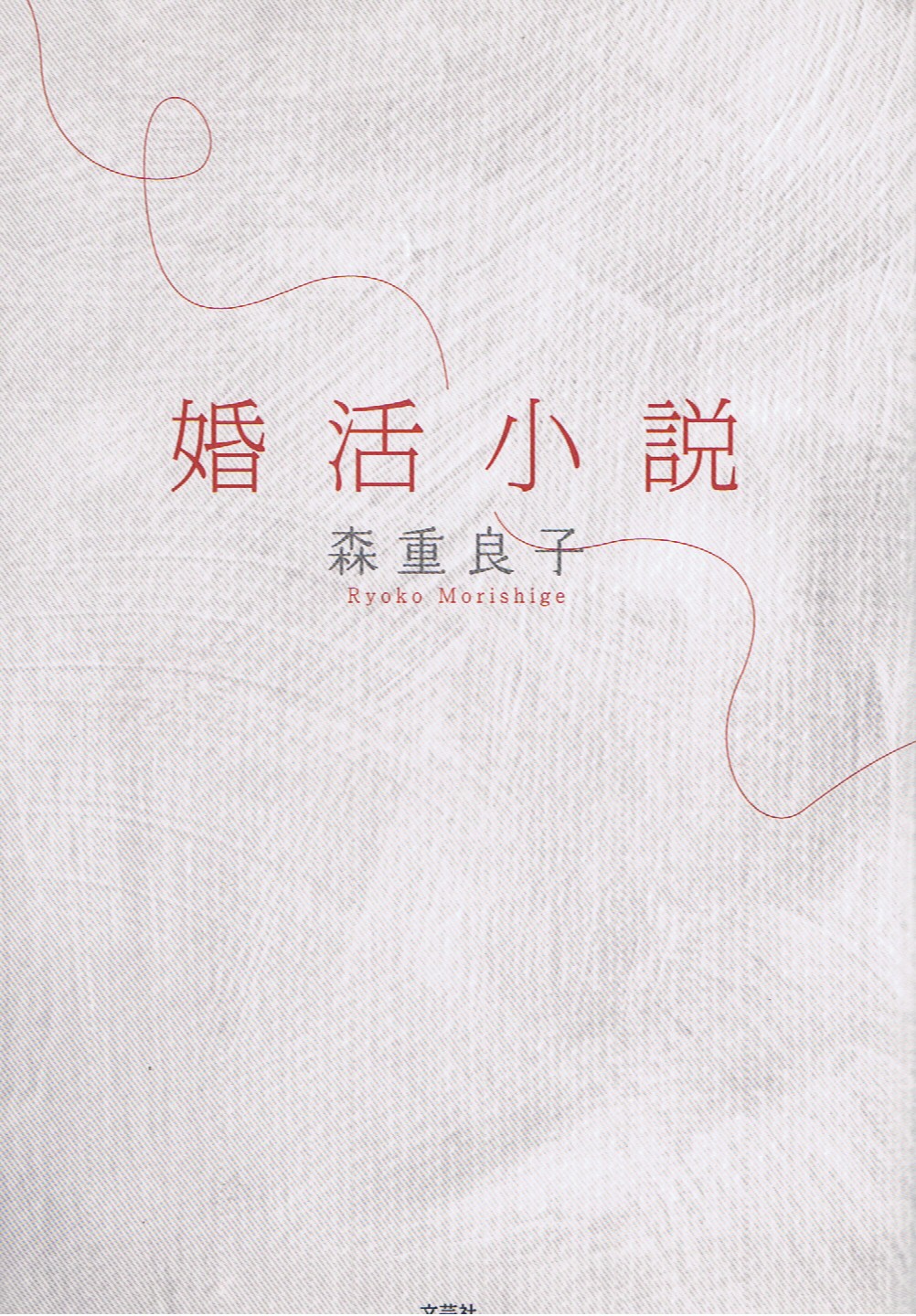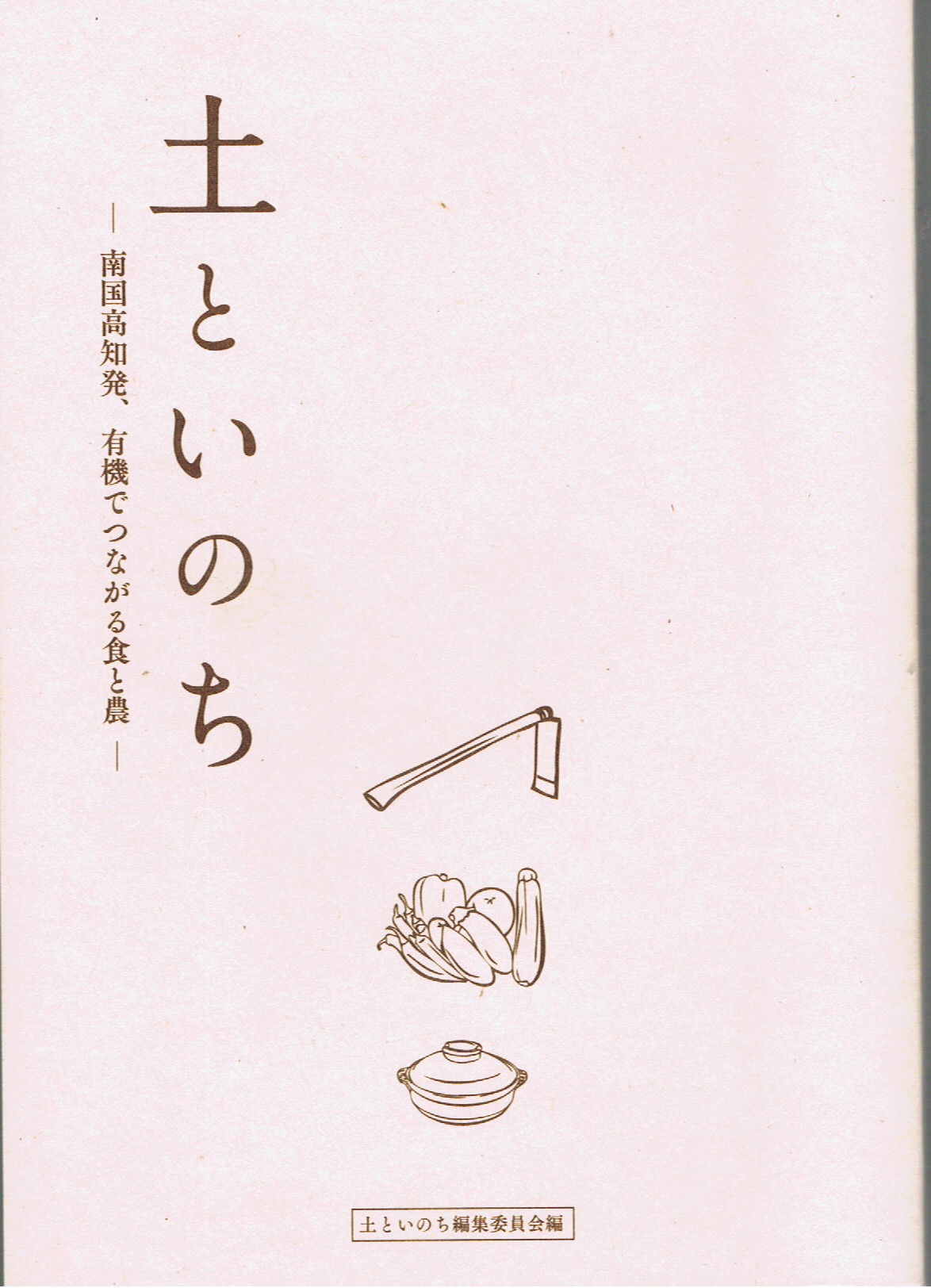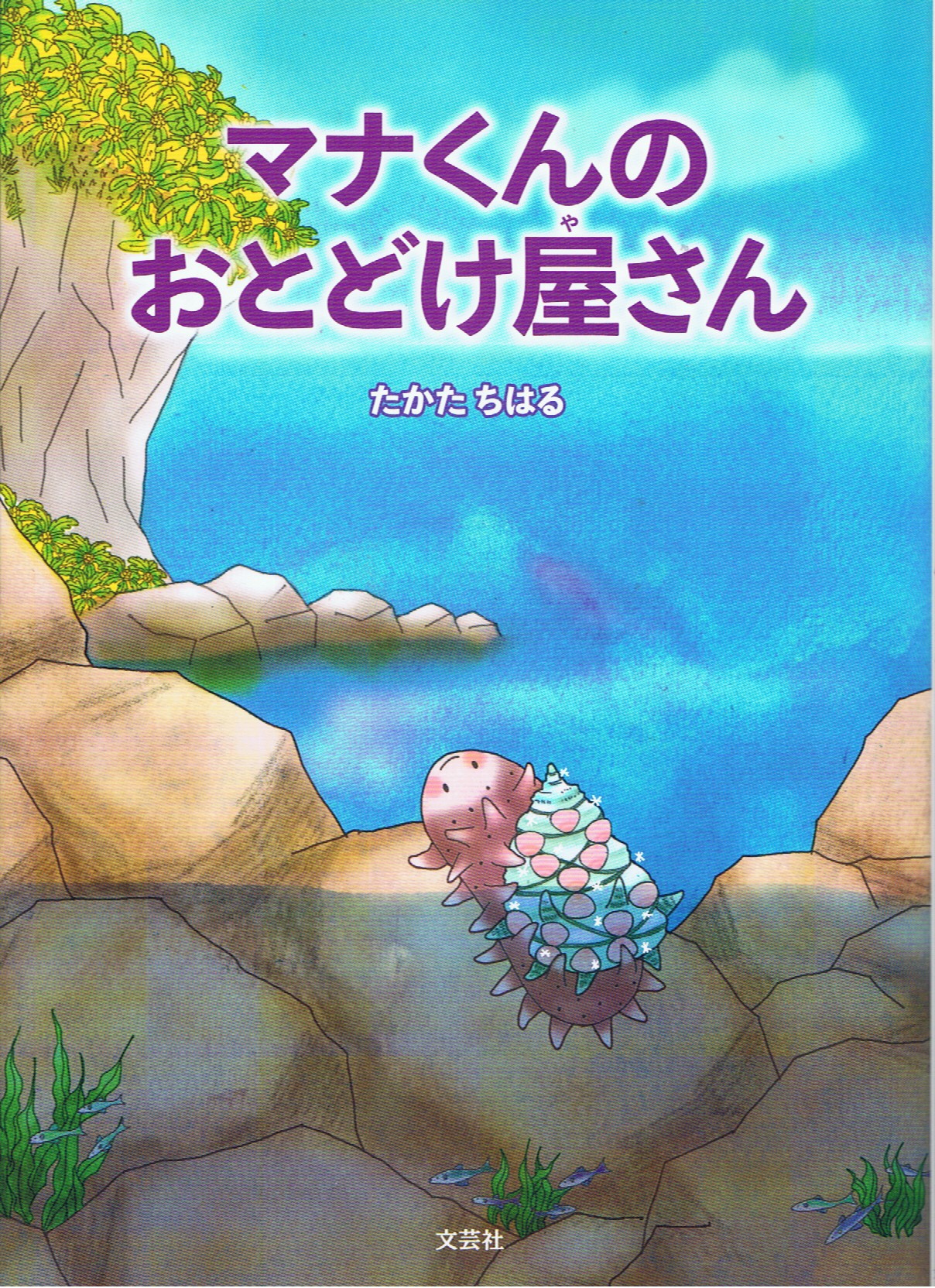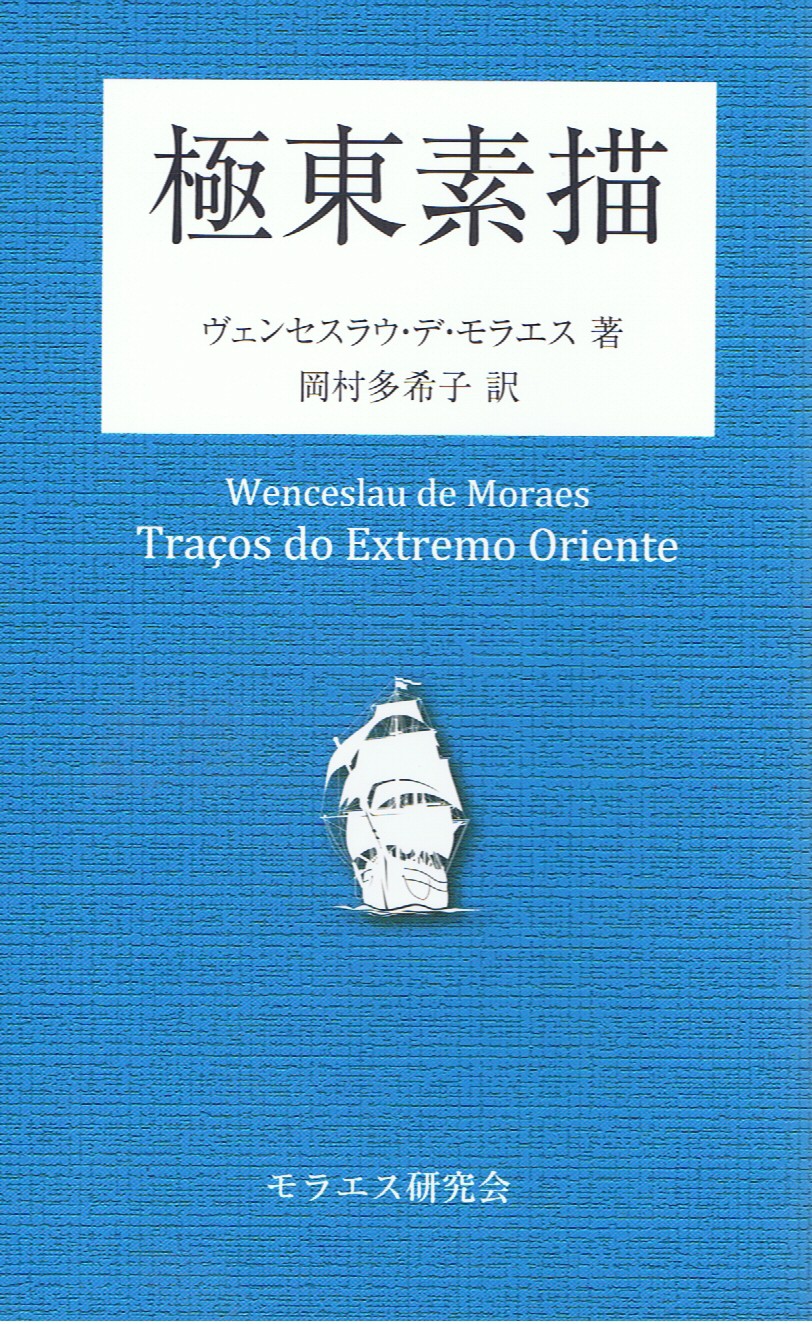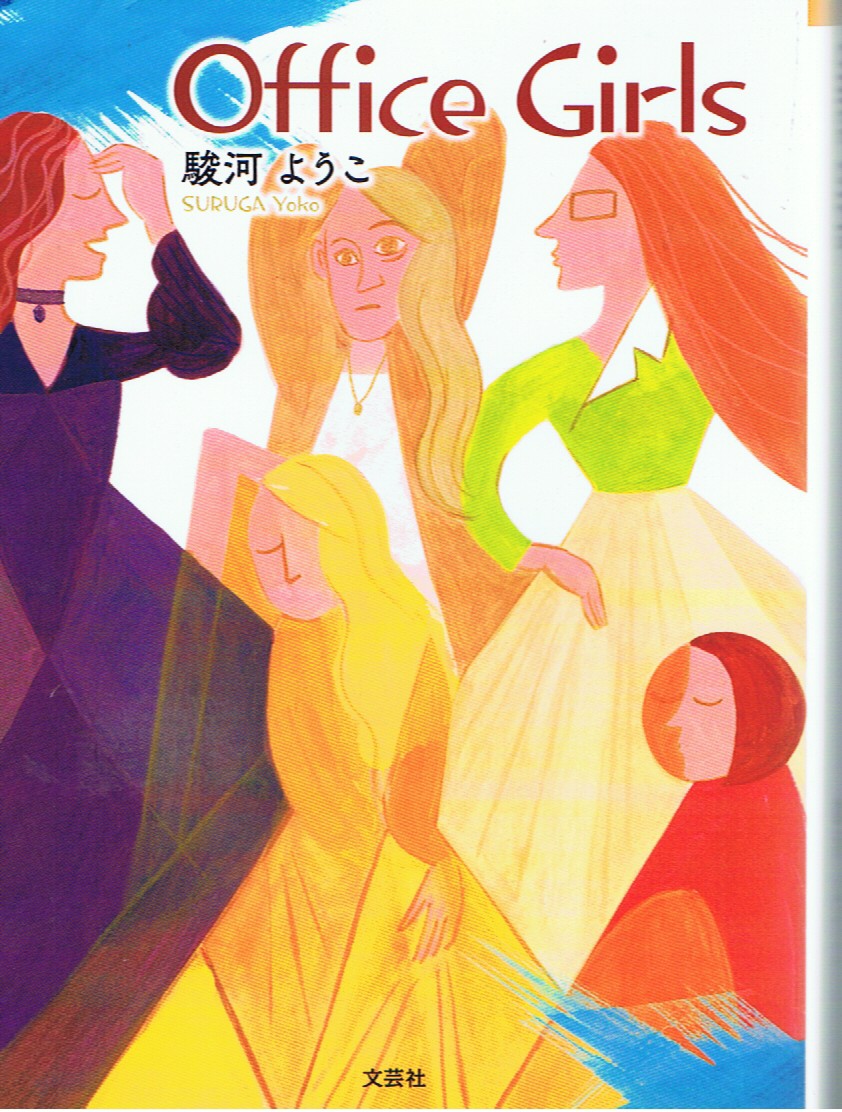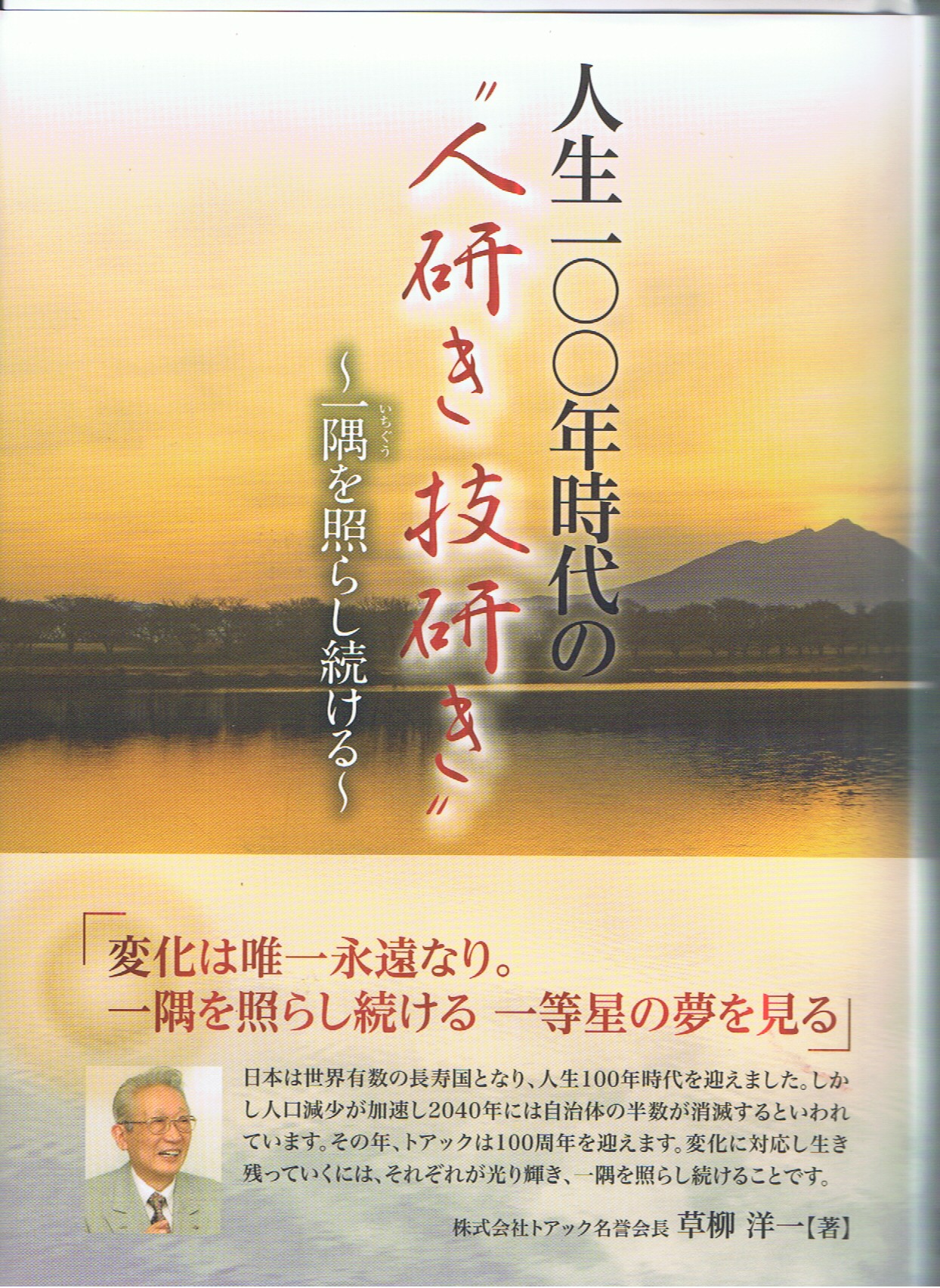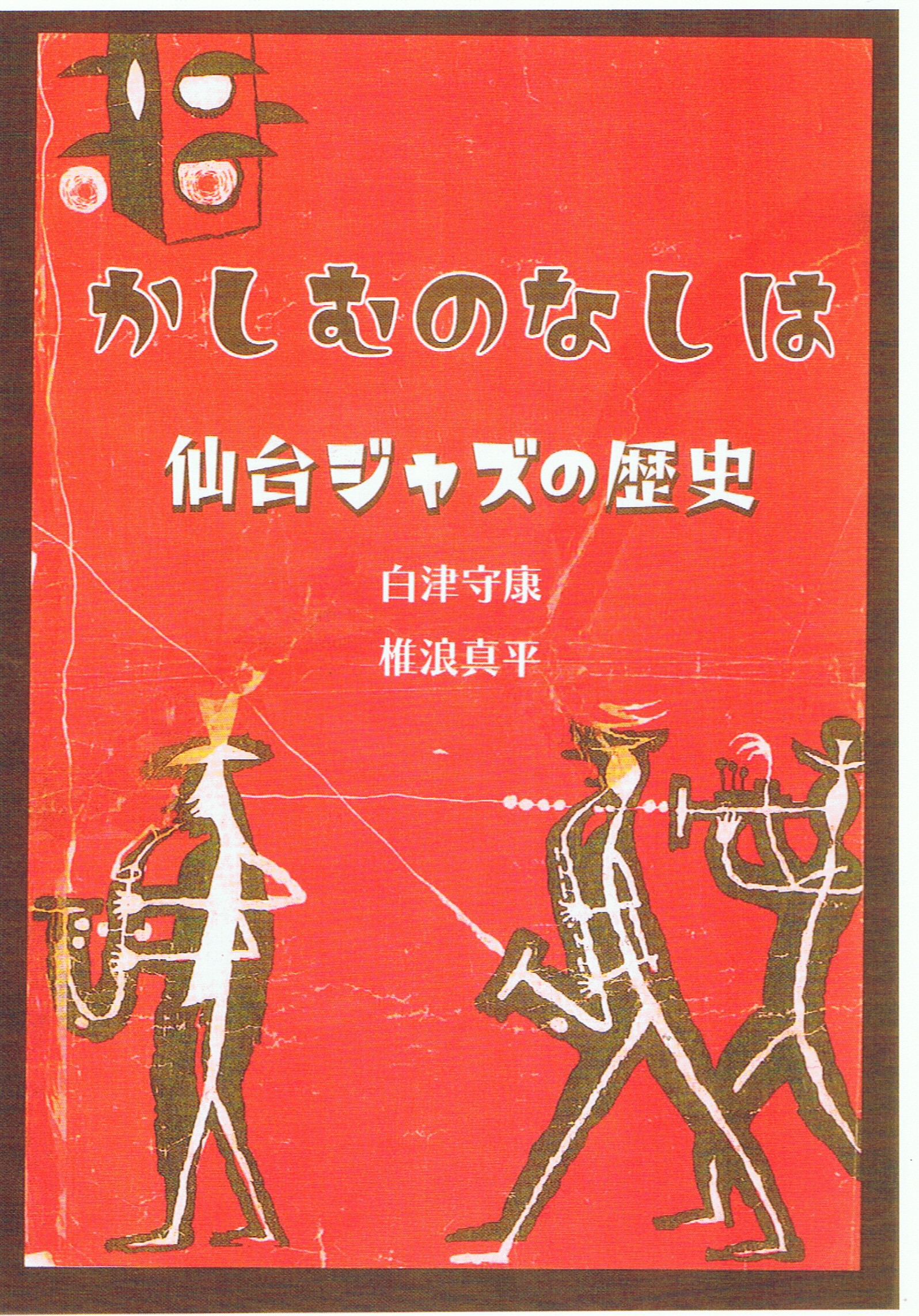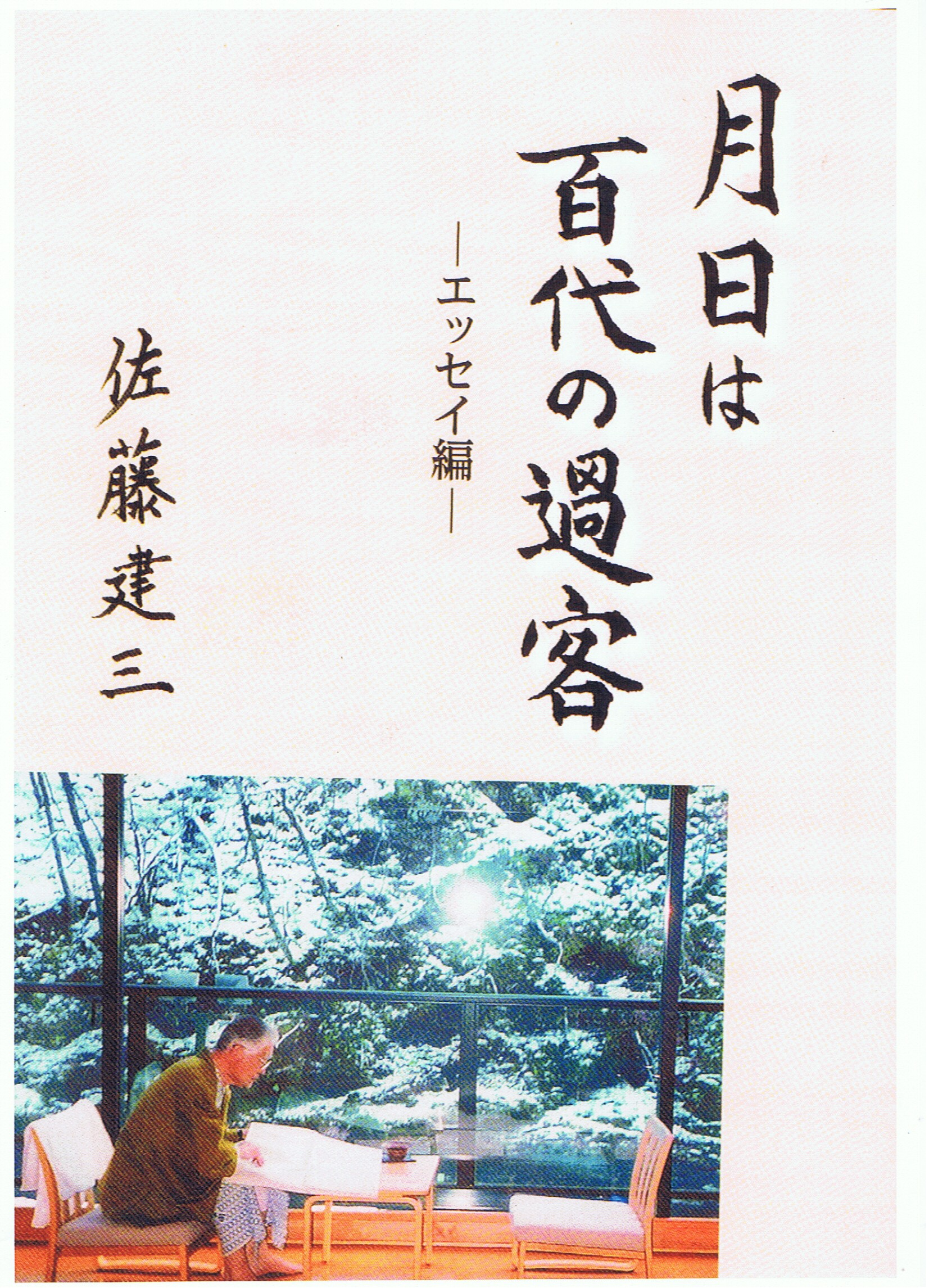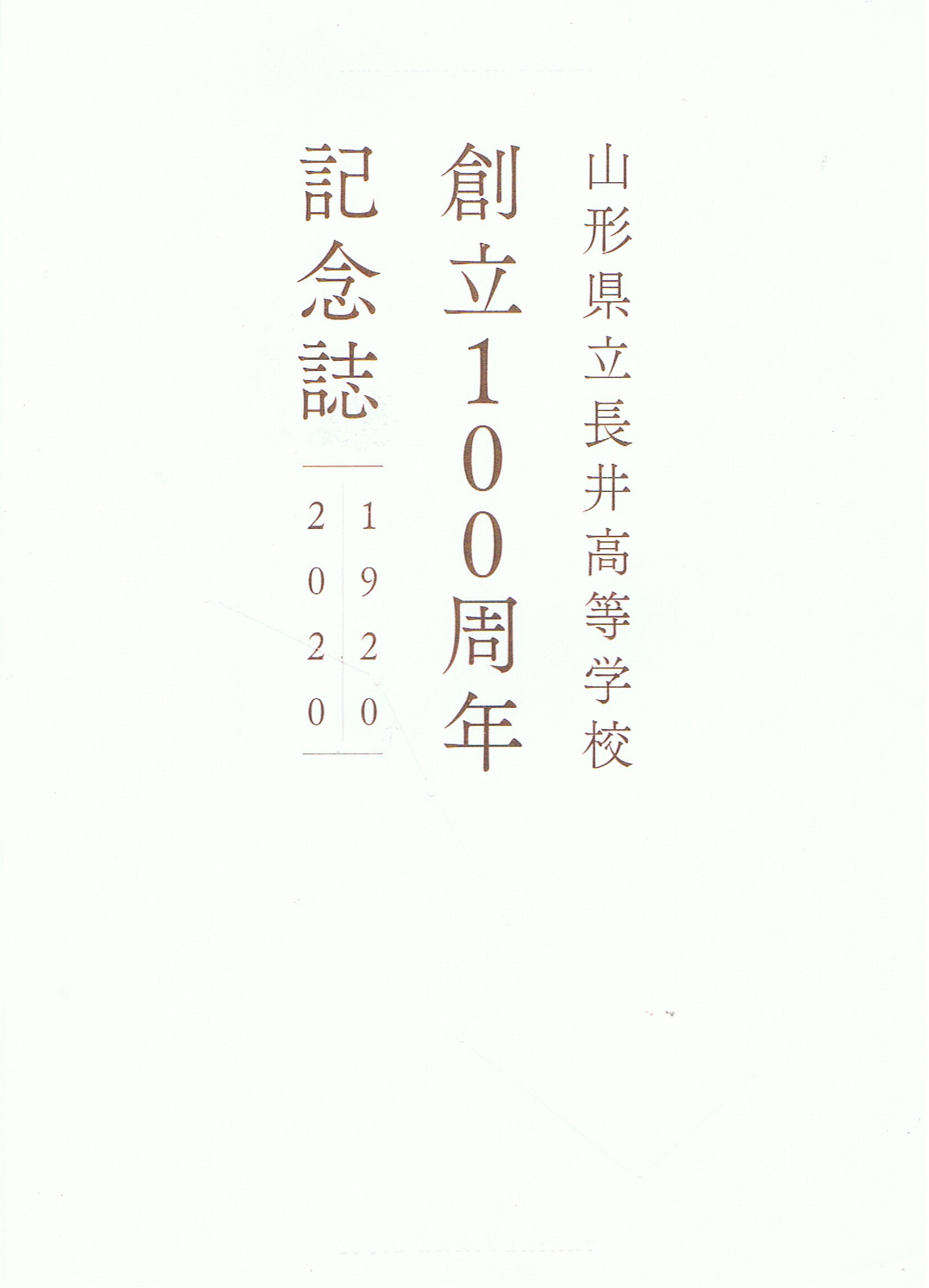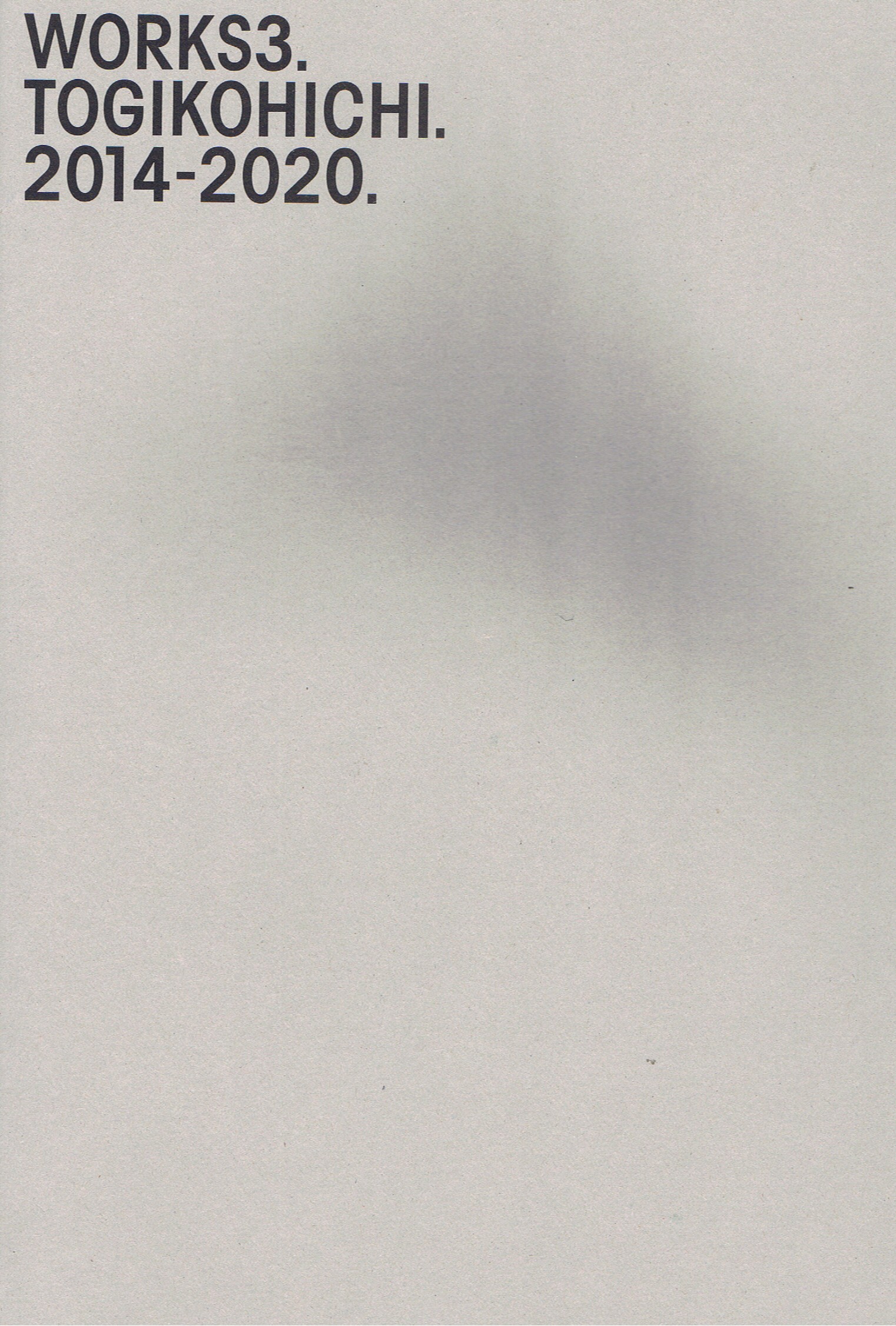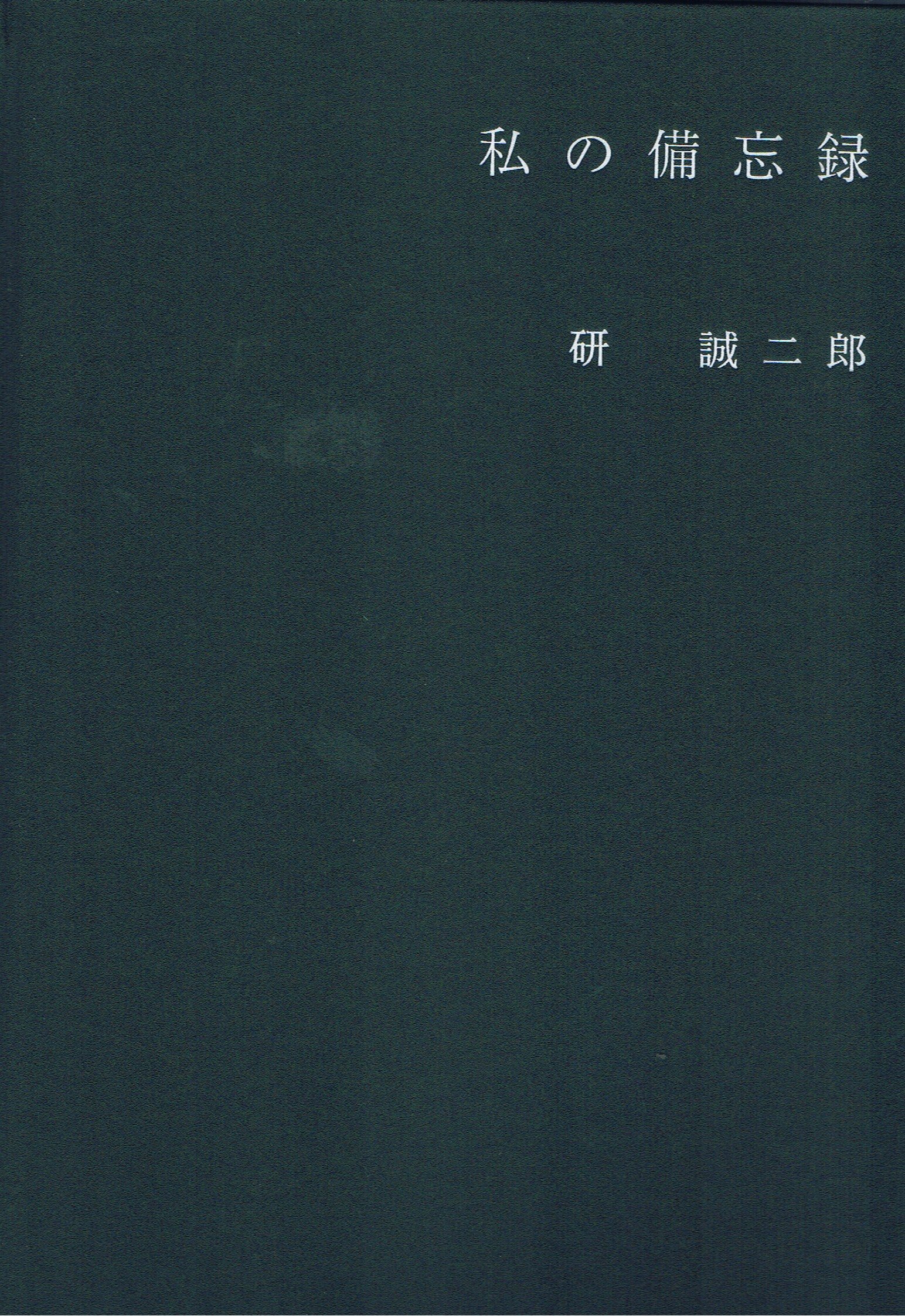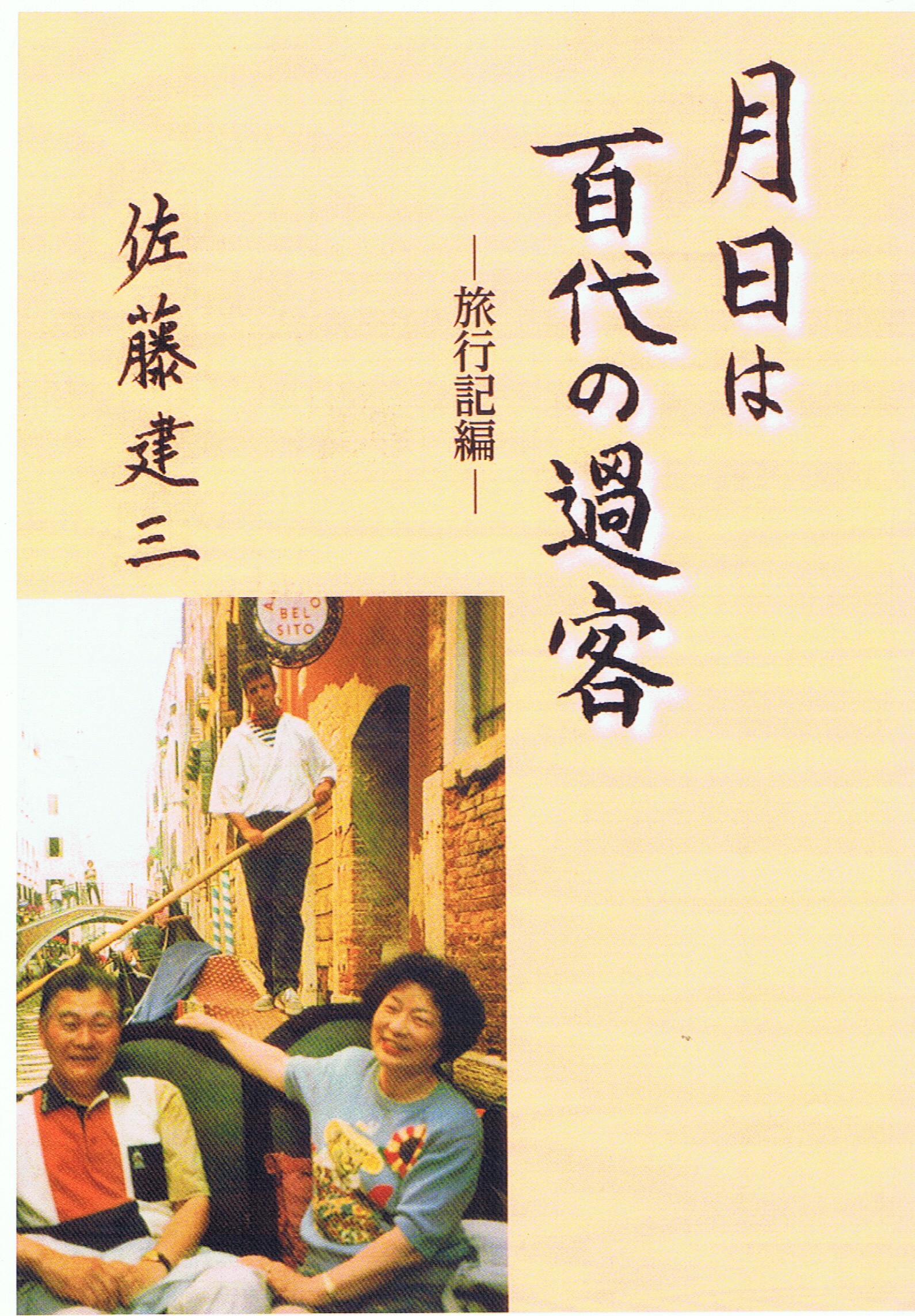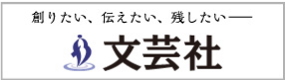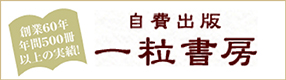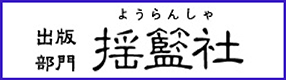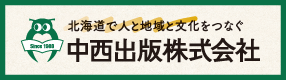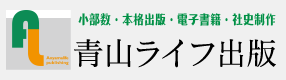- トップ
- JSNについて
- NPO法人日本自費出版ネットワークとは
- 日本自費出版文化賞
- 日本自費出版文化賞
- 過去の日本自費出版文化賞
- 日本自費出版文化賞へ応募
- 自費出版書籍データ
- 自費出版書籍データ検索
- 書籍データの登録方法と注意点
- 自費出版書籍データ登録
- 会員企業
- 会員企業情報 全会員
- 会員企業情報 役員
- 認定自費出版アドバイザー
- 出版契約ガイドライン
遵守事業者認定 - 自費出版アドバイザー制度
- 自費出版アドバイザー試験告知ビラ
- 自費出版アドバイザー講座
- お問合わせ
- 加入申込・文化賞資料請求・その他お問合せ
- 刊行物
- 自費出版年鑑
- バナー広告
- バナー広告について